こんにちは。今回はダックスフンド等に多いワンちゃんの椎間板ヘルニアについてお話しします。
椎間板ヘルニアは『背骨の脊髄が圧迫されることで神経に異常が起き、麻痺や痛みが出る病気』です。背骨というと背中や腰の症状が多いと思われがちですが、実は前肢、後肢の症状も多いのです。
例えば、後肢がもつれてうまく歩けない、後肢が痛い、散歩や抱っこを嫌がるなどといった様子になることがあります。重症化すると下半身の麻痺など障害がおこり、おしっこやうんちがうまくできなくなってしまいます。2~3日でどんどんひどくなっていくので早めに気が付いてあげることが重要です。
なるべく椎間板ヘルニアにならないようにするためにはどうしたら良いのでしょうか?それは背骨への負担を減らすことです。全力疾走する、何度もジャンプする、滑るなど背骨に負担をかける運動をさせないことです。ただし、適切な運動を行い、肥満にならないよう気を付けた方が良いでしょう。また、食事は適切な量を与えることも予防になります。
椎間板ヘルニアは再発率が高い病気ですが、日頃から予防を心がけ、早期に治療を開始してあげれば完治することも可能です。
メスの卵巣と子宮とを摘出する手術を避妊手術、オスの精巣を摘出する手術を去勢手術といいます。
 「不妊手術をするのはかわいそう」、「健康なのに手術する必要があるの?」、「自然にしておくのがいい」などの考え方もあるかとは思います。そこで、不妊手術についておはなしします。不妊手術は望まれない子犬子猫が産まれるのを防ぐということだけでなく、手術をすることでいろいろな病気の予防、ストレスを減らすという目的もあります。犬猫がより快適に、より長生きするために不妊手術は良い方法のひとつでもあります。
「不妊手術をするのはかわいそう」、「健康なのに手術する必要があるの?」、「自然にしておくのがいい」などの考え方もあるかとは思います。そこで、不妊手術についておはなしします。不妊手術は望まれない子犬子猫が産まれるのを防ぐということだけでなく、手術をすることでいろいろな病気の予防、ストレスを減らすという目的もあります。犬猫がより快適に、より長生きするために不妊手術は良い方法のひとつでもあります。
一方で手術には様々なリスクを伴います。
また、手術のあとやっぱり出産させてあげたいと思っても絶対に無理なことなので、もし少しでも赤ちゃんを産ませてあげたいという気持ちがあればもう一度考え直したほうがよいと思います。
これらのことを十分理解した上でご家族みなさんでよく話し合って決めるのがよいと思います。今回は簡単に不妊手術のメリット・デメリットについてお話したいと思います。。
【不妊手術のメリット】
まず不妊手術のメリットについてお話します
 メスの避妊手術を行うと、卵巣腫瘍、子宮蓄膿症、膣腫瘍などの病気の予防ができます。(乳腺腫瘍についても予防できる可能性もあると考えられます)。オスの去勢手術でも精巣、前立腺疾患などの病気が予防でき、会陰ヘルニア 肛門周囲腺腫などの病気の発症リスクが減ります。また、例えば糖尿病や犬アトピー性皮膚炎などの病気は発情期に悪化することがありますが、不妊手術をしていたおかげで症状が軽く済む場合もあります。
メスの避妊手術を行うと、卵巣腫瘍、子宮蓄膿症、膣腫瘍などの病気の予防ができます。(乳腺腫瘍についても予防できる可能性もあると考えられます)。オスの去勢手術でも精巣、前立腺疾患などの病気が予防でき、会陰ヘルニア 肛門周囲腺腫などの病気の発症リスクが減ります。また、例えば糖尿病や犬アトピー性皮膚炎などの病気は発情期に悪化することがありますが、不妊手術をしていたおかげで症状が軽く済む場合もあります。
さらに発情出血、偽妊娠、乳腺炎、マウンティング行動、スプレー行動などさまざまなストレスも不妊することで一生涯軽減できることもあるのです。ストレスがかかると発症してしまう様々な病気も予防できる可能性もあります。つまり不妊手術をした犬猫の方が不妊手術を受けていない犬猫より生活の質が向上し、寿命が長くなるかもしれないというのが最大のメリットなのです。
【不妊手術のデメリット】
 いっぽうの手術リスクとしては麻酔のリスクがいちばんにあげられます。
いっぽうの手術リスクとしては麻酔のリスクがいちばんにあげられます。
非常にまれですが、麻酔薬の副作用により肝臓、腎臓、脳、消化器、呼吸器、心疾患を患ってしまったり、麻酔薬に対するアレルギー反応がおこり、アナフィラキシーという状態になってしまうこともありえます。止血異常があると出血が止まらなくなることもあります。また、麻酔以外のリスクとして手術の後に癒着、癒合不全、感染、縫合糸に対しての免疫反応がおこってしまうということもあります。
それに手術直後は痛くてかわいそうなことがあります。しばらく痛みで元気や食欲がなくなる、一時的に排便排尿がうまくできなくなる、術創を気にして歩けなくなるなどといったこともありえます。また、手術後は肥満になりやすいので注意が必要です。
【手術デメリットをできるかぎりさけるために・・】
 手術のデメリットをできるかぎりさけるためには手術の前に健康診断、血液検査、レントゲン検査などを行います。肝臓、腎臓、貧血、感染症、止血異常、肺、心臓、気管などに異常が無いか調べ、可能な限りリスクを減らすことを心がけています。また、痛み止めのお薬を処方する、きずの治りが良い食事や肥満予防の食事を提案するなど術後のケアも大事だと思っています。
手術のデメリットをできるかぎりさけるためには手術の前に健康診断、血液検査、レントゲン検査などを行います。肝臓、腎臓、貧血、感染症、止血異常、肺、心臓、気管などに異常が無いか調べ、可能な限りリスクを減らすことを心がけています。また、痛み止めのお薬を処方する、きずの治りが良い食事や肥満予防の食事を提案するなど術後のケアも大事だと思っています。
 多くの方がフィラリア予防はしっかりされていますがノミ、マダニ予防はどうですか?
多くの方がフィラリア予防はしっかりされていますがノミ、マダニ予防はどうですか?
外に散歩しないから、他の犬と接触しないから、かゆがっていないから、みつけたら手で取るから、などの理由で必要ないと思っていませんか?
- ノミ、マダニは13℃になると活動を始めます。
- ノミ、マダニは室内でも発育します。
- ノミ、マダニは1匹でもアレルギーを起こすことがあり、すぐには気付きにくいです。
- ノミ、マダニを指でつぶすと寄生虫の卵や原虫がとびちる可能性があります。
- 寄生虫や原虫は人にも病気を引き起こします。
ぜひノミ、マダニ予防をしておきたいですね。

さて、みなさんは日常生活の中で定期的に健康診断に行っていますか?
ではワンちゃんネコちゃんの健康診断はしていますか?

人にもいろいろな病気があるようにワンちゃんネコちゃんにもいろいろな病気があります。人と同じように生活の中でどんなに健康に気をつけていても防ぐことのできない病気もあります。また、問診からわかる病気もありますが検査をしないとわからない病気もたくさんあります。
ワンちゃんネコちゃんの血液検査は人と同様に様々な検査項目があり、多臓器にわたる異常を見つけることが出来ます。
症状として出ていない病気を早期にみつけることもできます。ワンちゃんネコちゃんは言葉が話せないので飼い主さんが病気に気付いてあげることがほとんどです。しかし血液検査による健康診断を定期的にしてあげることでさらに飼い主さんも気付かなかった病気に気付くことができるかもしれません。
家族の一員であるワンちゃんネコちゃんが健康で長生きできるように病院で定期的な健康診断をしてあげるといいですね。
フィラリア検査に追加して特別価格で健康診断の血液検査ができます。
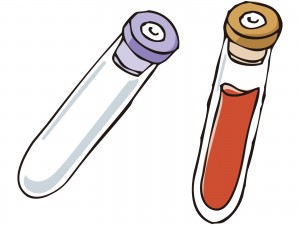
皆さん、ワンちゃん、ネコちゃんに「ホルモンの病気」があることをご知でしたか?
ホルモンの病気は、通常の健康診断血液検査などではみつけにくく、飼い主さんの問診から疑って見つかることが多い病気なのです。今回は、ワンちゃんのクッシング症候群、ネコちゃんの甲状腺機能亢進症という病気についてお話します。どちらもホルモンの病気のなかでも多い病気なので知っておくといいと思います。

まず、ワンちゃんのクッシング症候群について説明します。先ほど飼い主さんの問診で病気が見つかるというお話をしましたが、それはなぜかというと、この病気の1番多い症状は「水を飲む量が多い」ということだからです。獣医師は診察室でのワンちゃんの触診・視診だけでは「この子は水を多く飲みますね」とはわからないものです。獣医師は日頃からワンちゃんの様子をしっかり見ている飼い主さんに「この子はお水をよく飲みませんか?」と尋ねることで診断できるのです。他にもよくハアハアする、お腹がぽっこりしてきた、毛が抜けてうすくなってきたなどもこの病気の症状です。問診で疑いがでたら血液中のホルモン検査をしてみます。
クッシング症候群の多くは脳から出るホルモンが過剰になり、お腹の中の副腎という臓器からもホルモンが多くでてしまう病気なのです。放っておくとまれに様々な合併症や併発症、死に至ることもある病気ですが治療により多くは良好に維持できます。
次にネコちゃんの甲状腺機能亢進症は「この子、最近よく食べるのに痩せてきたし、怒りっぽくなってきた」という飼い主さんのひとことで疑いがでる病気です。他にも嘔吐、下痢、多飲、多尿、毛が薄くなってきたなどといった症状もありますが、漠然とした症状です。ワンちゃんと同じく問診で疑いがでたら血液中のホルモン検査を行い、診断します。
甲状腺機能亢進症は首のあたりにある甲状腺という臓器からホルモンが過剰にでて起こる病気です。
心肥大、高血圧、体力消耗などによりQOL(生活の質)を落としてしまいますし、甲状腺機能亢進症の半数が甲状腺の腫瘍であることがわかっていますので命にもかかわる病気です。
このように、診察だけではみつからない病気が他にもたくさんあり、飼い主さんからの問診が大事だということがおわかりかと思います。ワンちゃん、ネコちゃんがたくさんお水を飲む、怒りっぽくなったなど以前とは違う症状がある場合は早めに当院に受診してください。また、健康診断などの時にささいなことでも獣医師に相談してみることが大切かと思います。

最近お家のワンちゃんやねこちゃんの耳をチェックしましたか?汚れ、赤み、痒み、においはありませんか?
耳の病気は色々ありますが、特に犬猫がかかりやすい病気「外耳炎・中耳炎」について紹介します。
「外耳炎」とは、耳穴から鼓膜までの間に炎症が起こることをいいます。
鼓膜より奥に炎症が起こったものは「中耳炎」と呼ばれ、より重症で治りにくくなります。
外耳炎、中耳炎は主に細菌や酵母、外部寄生虫、アレルギー、腫瘍が原因で発症します。また、綺麗好きな飼い主さんに多いのですが、耳掃除のしすぎで耳の粘膜が傷ついて外耳炎になるケースもあります。外耳炎が慢性化すると中耳炎になることがわかっています。外耳炎を発症しやすい犬種があり、例えばアメリカン・コッカー・スパニエル、プードル、ビーグル、ダックス等がそれにあたります。
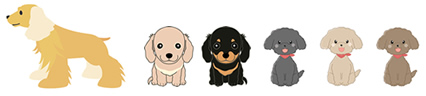
外耳炎・中耳炎になると痒みと痛みがでますので耳の付け根や耳穴を引っ掻いたり、頭や首を振ったり、耳を床や壁に押し付けたりします。重度の中耳炎の場合、顔が傾いたままになったりもします。
耳をチェックすると赤く腫れたり、黄色や茶色の耳垢がたくさん見られたり、独特なにおいがしたりします。
もし、このような症状がみられた場合はワンちゃん、ねこちゃんと一緒に当院へご来院下さい。当院では耳鏡検査・耳垢の顕微鏡の検査で診断し、点耳薬や飲み薬等で治療します。また、定期的な耳掃除をすすめる場合もあります。外耳炎は早めに発見し、原因をきちんと調べそれに合った治療を行えば大部分は良くなります。定期的に耳掃除をしたり、病院で健診することが大切です。
耳掃除の時に使用するクリーナーを取り扱っておりますので気になる方は獣医師、スタッフにお申出下さい。

オーツイヤークリーナー











